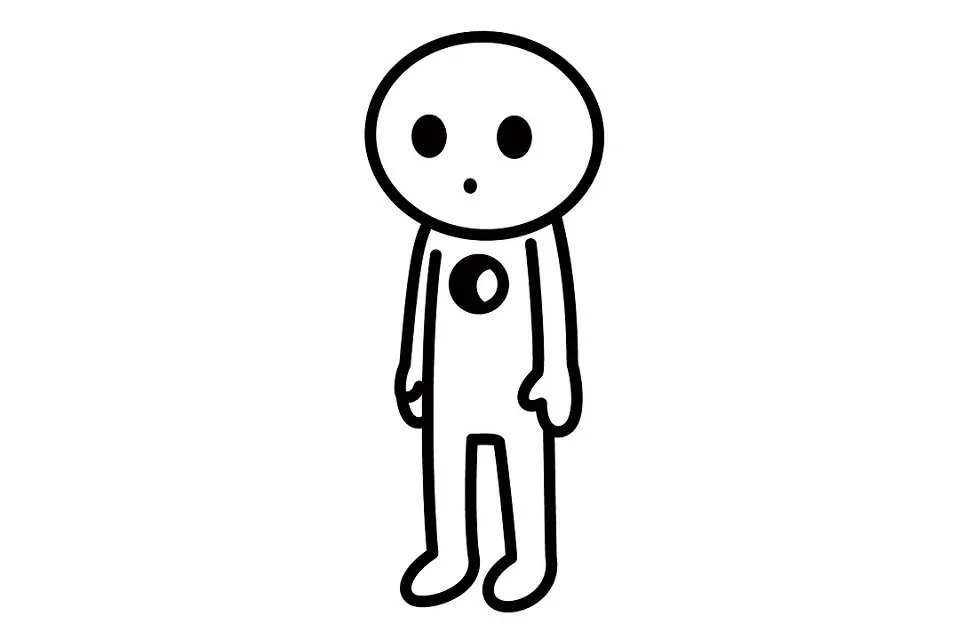夢十夜(夏目漱石)のあらすじ

夢十夜は1908年に発表された夏目漱石の連載小説です。 各話独立した全十話の夢の話で「こんな夢を見た。」から始まる夢の内容を描いた作品です。
この物語は漱石が実際に見た夢なのか、そういう設定の創作物語なのかはよく分かっていません。 夢の話と言うだけあって突拍子のない話ばかりですが、それ故にどこか心惹かれるところがあります。
第一夜
こんな夢を見た。
枕元に座っていると、仰向きに寝た女が「もう死にます。死んだらまた逢いに来るから墓の側で待っていてください」と言いました。 いつ逢いにくるかと尋ねると百年待っていて下さいというので、待っていると伝えると女は死にました。
墓を作ってその傍らに座り、日が昇って沈むのを数えながら待ちました。 やがていくつ数えたか分からなくなり、苔の生えた丸い石を見て、女に騙されたのではないかと思い始めました。
すると石の下から茎が伸びてきて、自分の胸の辺りに留まると一輪の白い百合の花が咲きました。 私は百合に接吻し遠い空の星を見て、もう百年経っていた事に初めて気づきました。
第二夜
こんな夢を見た。
私は寺の和尚に「侍なのに無を悟れない」と馬鹿にされ、悔しければ証拠を持って来いと言われました。
侍がこうまで恥をかかされたら、悟りを開いて和尚を切り捨てるか、さもなくば腹を切って死ななければなりません。 置時計が次の刻を打つまでに悟りを開いてみせると自分の部屋に戻り瞑想を始めました。
無を念じているのに線香の匂いがします。 歯を食いしばり拳骨で頭を殴り、痛くて苦しんでも無は出てきません。 そのうち頭がおかしくなって何もかもが有って無いかのように見えましたが、しかし無は現れません。
時計がチーンと鳴り始め、すぐに短刀に手をかけました。 やがて時計が二つ目をチーンと打ちました。
第三夜
こんな夢を見た。
六歳になる我が子を背負っており、子の眼は潰れていてまるで大人のように話します。 子は眼が見えないのに周りの風景を言い当て、恐ろしさを感じた私は森に子を捨ててしまうことにします。 そう思うと子はふふっと笑い「お父さん重いかい?今に重くなるよ」と言います。
背中で独り言のように心を見透かしてくる子を背負いながら、森に入りやがて杉の木の前に辿りつきました。 すると子が「お前が俺を殺したのは丁度100年前だね」と言うや否や、私の頭に100年前に盲人を殺した記憶がよみがえります。 その途端に背中の子が石地蔵のように重くなりました。
第四夜
こんな夢を見た。
土間の片隅に酒を飲んでいる爺さんがいて、川原の方へ行くと言って表に出ます。 爺さんは柳の下にいる子どもたちに「手ぬぐいが蛇に変わるから見ておけ」と笛を吹き始め、子どもたちは一生懸命見ていましたが一向に変わる気配がありません。
やがて手ぬぐいを肩にかけた箱にいれて「こうするとやがて蛇になる」と言って再び歩き始めました。
今になる、今になると歌いながら川岸に付き、そこで見せてくれるのかと思えば爺さんは川へと入っていき、やがて水に浸かって姿が見えなくなりました。私は爺さんが向こう岸に着いたら蛇を見せてくれるだろうと待っていましたが、とうとう爺さんは上がってきませんでした。
第五夜
こんな夢を見た。
神代に近い昔、戦に敗れた私は生け捕りになって敵の大将の前へと連れられてきました。 大将は降伏するか死ぬかを迫って来たので、私は死ぬと答えます。
ただ死ぬ前に恋人に会いたいと申し出ると、夜が明けて鶏が鳴くまで処刑を待ってくれることになりました。 恋人は私に会うため急ぎ馬を走らせましたが、道中で鶏の鳴く声に動揺して馬の操作を誤り淵へと落ちていきました。
実は鶏の声は天邪鬼の声真似でした。
第六夜
仏師の運慶が護国寺の山門で仁王を刻んでいるという評判を聞き、行ってみると大勢の人が見物や批評をしていました。 運慶は鎌倉時代の人物ですが見ている我々は明治の人間で、私はどうして運慶が生きているのか不思議だと思っていました。
見物人は好き勝手に仁王像のことを話していましたが、運慶は何も感じない様子で仁王を彫っています。 すると男が「あれは仁王を掘っているのではなく、木に埋まっている仁王を掘り出しているだけだ」と言っています。
それを聞いた私はそれなら誰にでもできるのではないかと、一つ自分で仁王を掘り出してみることにしました。 家にあった木を彫ってみましたが、彫っても彫っても仁王は見当たりません。
明治の木には仁王は埋まっていないと悟り、今日まで運慶が生きている理由が分かりました。
第七夜
何か大きな船に乗っていますが、どこに行くのか分かりません。 船員に聞いても要領を得ず、いつ陸に上がれるのかも分かりません。
私は大変心細く、こんな船にいるよりいっそ死んでしまおうかと思いました。 乗客は沢山いましたが、私の慰めにはなりませんでした。
それでますますつまらなくなった私はとうとう死ぬことにして、ある晩に船から海に飛び降りました。 しかし船と縁が切れた刹那に命が惜しくなって後悔しましたがもう遅く、どこに行くか分からない船でも乗っていた方が良かったと思いながら黒い波の彼方へと落ちていきました。
第八夜
床屋に入ると白い着物を来た三、四人が一斉にいらっしゃいと言いました。 床屋には六枚の鏡があり、椅子に座ると鏡を通して窓の外を通る人がよく見えました。
髪を切ってもらいながら鏡を眺め、往来を通り過ぎていく人々を見ていました。 しばらく眺めていると大金を数えている女が映り、散髪の合間に直接見てやろうとしましたがその時にはもう窓の外に女はいませんでした。
代金を払って出ると外には金魚売りがいて小桶に入った金魚が並べてありました。 金魚売りは金魚を見つめたままじっとしており、しばらく眺めていましたがその間金魚売りはちっとも動きませんでした。
第九夜
世の中が何となくざわつき、今にも戦争が起こりそうでした。 屋敷には若い母と三つになる子がおり、夫は侍で月の無い夜に出たきり帰ってきません。
毎日夜になると母は幼い子を連れ、夫の無事を願いに八幡へに出かけていました。 まずお祈りをしてその後は御百度を踏んで、夜も寝ずに夫の無事を願っていました。
しかし夫はとうの昔に浪士に殺されていました。 こんな悲しい話を夢の中で母から聞きました。
第十夜
庄太郎が女にさらわれてから七日目の晩、ふらりと帰ってきて熱を出して倒れました。 庄太郎は至極善良で、水菓子屋の前で女を眺めるのを道楽としている男でした。
庄太郎は水菓子屋で買い物をした女の荷物運びを手伝い、それ以来行方不明になっていました。 探していた友人と親戚は今までどこにいたんだと問い詰め、庄太郎は答えます。
庄太郎は女に付いて電車で移動し、原っぱを通って絶壁の上に案内されて「ここから飛んでみなさい」と言われました。 それを断ると「何万もの豚に襲われるがよろしいか」と言われ、しかし命には代えられないと飛び下りませんでした。
そこへ豚がやってきたので、ステッキで鼻づらを殴ると絶壁の下へと落ちていきました。 するとまた一匹また一匹とやってきて、ふと気づくと見渡す限り辺りが豚だらけで、それが庄太郎めがけて向かってきます。
庄太郎は心底恐怖しましたが、仕方ないので一つ一つ丁寧に豚を叩きのめしていきました。 そして六日目か七日目かの晩についに精魂尽きて倒れました。
健さんは「だからあまり女を見てはいけない」と言い、自分もそれをもっともな意見だと思いました。 庄太郎は助からないでしょう。
感想
以上が夢十夜でしたが、読んで理解できたでしょうか? 多分「訳が分からない」というのが正直な所だと思いますが、実際本編を読んでも訳が分からない部分が多いです。
私の読解力が足りないのもあるかもしれませんが、一度読んだだけで理解できる内容とは思えませんし、何度読んでも分からない所は分かりません。 だから私のあらすじが悪いせいではないのです。多分…
夢を文章に起こせばこんなものだろうと割り切って、文字を読むのではなく感覚的に読むのが良いのではないでしょうか。 中には話の解説や考察をしている人もいるので、より深く知りたい方はそちらに当たっていただければと思います。
これらを実際に漱石が見た夢、あるいは考えている事という体で心理分析されたりもしています。 私は専門家ではないので真偽はよく分かりませんが、漱石の心の考察は中々に興味深いものがあります。